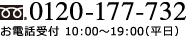初心者必見!マンション経営を失敗させないための不動産投資入門
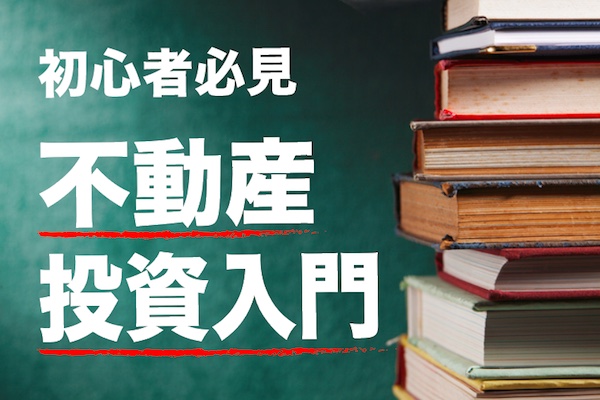
(写真=PIXTA)
マイナス金利が日本にも導入されたことで、不動産投資への関心が高まっています。とりわけ、マンション経営は投資用住宅ローンの金利が低下傾向にあることで、千載一遇のチャンスという専門家もいます。
そこで、初心者が失敗しないための不動産投資、なかでもマンション経営について、10個のテーマに分けて解説します。
今がチャンスと言われている「マンション経営」の理解を深めてください。
1章 マンション経営(不動産投資)のメリット
2章 マンション経営を失敗させないための儲かる物件の選び方
3章 マンション経営を失敗させないためにはデザイナーズマンションがいいと言われる理由
4章 マンション経営を失敗させないための物件の管理方法
5章 マンション経営を失敗させないための初期費用、諸経費の知識
6章 マンション経営を失敗させないための税金の知識と節税対策
7章 マンション経営を失敗させないためのリスクへの知識と対応
8章 マンション経営の利回りを理解して、収入を確保するための方法
9章 マンション経営を失敗させないための資格や情報収集方法
10章 マンション経営の始め方
1章 マンション経営(不動産投資)のメリット
 (写真=PIXTA)
(写真=PIXTA)
不動産投資が、いま注目されることには大きな意味があります。みなさんご存知のように、世の中には株式、投資信託、債券、外貨投資など、様々な投資商品があります。これらの金融商品の大半が、現在の「マイナス金利導入」によって、これまでのトレンドが一変し、将来の見通しが立ちづらい状況に陥っています。
そんな中で、注目されているのが「マンション経営」をはじめとする不動産投資です。では、マンション経営にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
>> 不動産投資のメリット6つ
● メリット 1 : 家賃で安定収入が得られる
マンション経営の最大のメリットが「安定収入」です。マンション経営は毎月安定した家賃収入が得られます。
● メリット 2 : 少ない自己資金で投資がスタートできる
マンション経営ではローンを組むことが一般的なので、初期にかかる頭金は低く抑えることができます。他の不動産投資と比べても初期費用を抑えられるので、マンション経営は比較的少ないリスクで運用できるメリットがあると言えます。
● メリット 3 : 生命保険の代替商品になる
不動産投資でローンを組むと、「団体信用保険」と呼ばれる生命保険に加入することが義務付けられています。万が一、ローン返済中に病気や事故で死亡した場合、「残債」は保険によってカバーされます。残された家族は、マンションが資産となります。
>> マンション経営によって期待できる、生命保険としての効果とは?
● メリット 4 : 「老後資金」の代わりになる
自分が退職した頃にはローン返済も完遂し、物件はそのまま自分の老後資金として残ることになります。つまり、わずかな自己資本のみ、ほとんど自己負担なしで大きな老後資金を作ることができるわけです。
>> 老後、安定的な収入を得るためには
>> マンション経営によって年金と同じ役割を期待できる?
● メリット 5 : 節税効果がある
マンション投資の大きなメリットが、この節税効果です。毎年の「確定申告」で、不動産所得が赤字になれば他の所得から赤字分を差し引くことができる「損益通算」によって節税効果が期待できます。
さらに、生前に財産を贈与した場合にかかる「贈与税」、死後の相続にかかる「相続税」でも、現金に比べて税が安くなります。たとえば、土地部分は国税庁が発表する「路線価」によって評価されますが、路線価は時価とほぼ同じ「公示価格」の約80%程度の評価と言われます。同様に、建物も時価の60%程度と言われる「固定資産税評価額」によって評価されます。評価額が低い分、節税効果が出るわけです。
● メリット 6 : 購入価格より高く売れれば「売却益」が得られる
80年代後半の不動産バブル時代のように、どんな物件でも値上がりして売買益がでるという時代ではありませんが、投資のタイミングなどによってはキャピタルゲインを得ることできます。
そのためには、「投資する物件の選別」「購入後の管理運営」「売却時のタイミング」といった3つのポイントで失敗しないことが大切です。自分自身で不動産投資の正しいノウハウを身に付け、信頼できるビジネスパートナーと巡り合うことも重要になります。
>> マンション経営は何故インフレに強いと言われるのか?
2章 マンション経営を失敗させないための安全な物件の選び方
● 新築マンションか中古マンションか
マンション経営をするなら、新築マンションを選んだ方が安定した賃貸収入を得られるケースが多いです。
>> 新築ワンルームと中古ワンルーム、投資マンションとしてはどちらがお得なのか?
価格は新築の方が高いですが、築浅の中古であれば新築とさほど変わらない場合もありますし、大事なのは購入価格よりも「賃貸需要」です。
>> マンション投資が失敗する理由と、失敗しないためのマンションの選び方
新築は担保価値が高く、融資を受けやすくなるのも大きなメリットと言えるでしょう。他方、中古マンションの場合、修繕費が上昇するリスク、劣化具合によっては空室率が上昇するリスクを考慮しなくてはなりません。
>> 不動産投資、銀行マンが融資したくない物件の5つのポイントとは?
最近では外国人観光客の増加に伴い、Airbnbに代表される「民泊」が注目されています。現在、分譲マンションで民泊の営業をすることは、国家戦略特区などを除き旅館業法に抵触する可能性があります。
>> 投資したマンションで、Airbnbの利用は問題があるのか?
● マンションか戸建てか
不動産投資での物件種別の選択は、長期的に考えるとマンションの方が戸建住宅よりも耐久性が高く、管理に手間がかかりません。そのため、貸しやすく高い稼働率が見込めるものと言えます。
>> マンションの寿命はどれくらい?
他方で、賃貸物件の供給は戸建てに比べてマンションの方が圧倒的に多く、競合物件も多いです。戸建ての場合はファミリー層に需要が限定されるため、空室となるリスクはどうしても高くなります。これに対し、都内などでは単身者の世帯は増えていますので、ワンルームマンションは底堅い需要が見込めるでしょう。
>> 不動産投資物件、マンションと戸建てのどちらが良い? メリット、デメリットを徹底解説
● 安心なマンション経営の立地条件
安心してマンション経営を行う上で重要な立地条件を挙げてみます。
「駅から近い」 : 駅から近いほど資産価値が落ちにくく、空室リスクや家賃下落リスクを抑えられます。
「生活利便施設」 : 周辺にスーパーや金融機関があると、長く居住してくれる方が多くなります。
「住環境」 : 緑や公園が近くにあるといったことや、騒音がないかといった環境も大事な要素です。
>> 資産価値が高いマンションの5つの特徴とは
こうしたマンション経営を失敗しない物件の選び方は、すべての要素が満たされている必要はありません。これらの条件の中で一つでも抜きんでていれば、物件の価値は長期に渡って維持される可能性が高いと言えます。
3章 マンション経営を失敗させないためにはデザイナーズマンションがいいと言われる理由

では、実際にどんな物件に投資をすればマンション経営を成功できるのでしょうか。近年人気の「デザイナーズマンション」について解説します。
>> 不動産投資は入居率100%のデザイナーズマンションにしなさい!
● 専門家が「快適な住空間」にこだわったマンション
デザイナーズマンションというのは、建築家や設計者が建物の外観や内観の意匠を凝らし、工夫を重ねた個性的なマンションのことです。業界では「デザイナー物件」と呼ばれていますが、建物の外観や間取り以外の家具や設備、壁紙といった建物全体に、独自の工夫や創造を加えたマンションと言ってよいでしょう。
デザイナーズマンション=コンクリート打ちっぱなしの外観、というイメージがありますが、外観だけではなく、床や壁の素材にこだわり、キッチンや洗面化粧台にも人間工学的に考えられたものを使うことで「より快適な空間づくり」のための工夫が凝らされています。
そんなデザイナーズマンションには、当然のことながら物件価格は割高になり、「賃貸料」なども割高に設定されます。割高では入居者探しに苦労すると思われがちですが、実は割高な家賃になっても住んでみたいと思う人が多いのも事実です。「他人とは異なる部屋に住んでみたい」「既存の概念にとらわれない自由な空間に住んでみたい」という人が多く、家賃にはこだわらずに借りたいというニーズが一定の範囲で存在するのです。
>> よく耳にする「デザイナーズマンション」とは実際どんなもの?
● ランニングコストを抑えられる
さらに、デザイナーズマンションの特徴として、ランニングコストが割安というメリットがあります。コンクリート打ちっぱなしの建物では、外壁やコンクリートの内側に立てるボードやクロスを最小限にすることができ、入退去後のリフォームが少ない、将来のメンテナンスコストも抑えられるという特徴があるのです。
くわえて、デザイナーズマンションに入居を希望する人というのは、ある程度生活にゆとりのある人が多く、家賃を滞納、室内をひどく汚される、といったリスクが少ないとも言われています。要するに現在は、他の人とは違う、個性を大切にしたい、そんなニーズが高いことを意味しています。マンション経営には、こうした人々の考え方の変遷を読み取ることも大切な要素になります。
4章 マンション経営を失敗させないための物件の管理方法
マンションの賃貸経営について大切なのは、家賃収入の安定確保です。そのためにオーナーが常に注意を払っておきたいのが「空室リスク」です。空室になっても、すぐに次の入居者が埋まる対策や工夫が必要になります。
>> 空室率を下げるためにマンションオーナーがすべきこととは?
● サブリースとは?
では、空室率を下げるための対策とは何でしょうか。その方法として注目されているのが「サブリース方式」です。
>> マンション経営の管理手法、サブリースとは何?
サブリースとは、オーナーが所有するマンションを「サブリース会社」が一括して借り上げて運営する方法です。オーナーは、サブリース会社から毎月定額の借り上げ賃料を受け取れます。入居者の有無にかかわらず家賃に相当する借り上げ賃料を受け取ることができ、加えて入居者の募集から契約、更新手続き、集金、退去の立合いなど、煩わしい業務をすべて代行してもらえます。賃貸人とのトラブルや建物の管理なども一括して代行してくれる場合がほとんどです。
>> 管理会社に何を管理してもらえるのか? 委託できる不動産物件の維持・管理業務
● 空室率を下げるためのマンション選び
サブリースはマンションオーナーにとって魅力的な契約ですが、大切なことはいずれ「契約終了」になることです。
>> 退去者が出た時の対応方法
契約終了後も、きちんと家賃収入を稼ぎ出してくれる魅力ある物件を購入することが求められます。では、どうすれば空室率の低い物件を選ぶことができるでしょうか。大きく分けて6つのポイントがあります。
① 人気あるエリアの物件を購入すること
② 立地が良く、住みたいと思う魅力ある物件を選ぶこと
③ 行き届いた管理をしてくれる管理会社を選択すること
④ 適正な家賃相場をリサーチすること
⑤ 集客能力の高い賃貸仲介業者を見つけること
⑥ 複数物件の所有とサブリース契約
マンション経営を安定的に推進して行くためには、複数の物件を所有して「空室リスク」を分散する。あるいは「サブリース契約」を結んで空室リスクを管理することです。こうした努力が、マンション経営を成功に導きます。
5章 マンション経営を失敗させないための初期費用、諸経費の知識
マンション経営を行うためには、物件購入にかかる初期費用はもちろん、さまざまな経費が必要になります。経営を成功させるにはまず経費をしっかり把握しておきましょう。
● 初期費用
マンション経営に必要な初期費用には、以下のものがあります。
>> マンション経営を始めるための初期費用
・ 頭金 : 自己資金と月々の返済額を計算した上で、頭金を設定
・ 仲介手数料 : 仲介業者に支払う手数料 (新築のマンションの場合は不要)
・ ローン関係費用 :ローンを組んだ場合、手数料や保証会社に支払う保証料などの費用
・ 登記関係費用 : 「所有権移転登記」や、「抵当権設定登記」に支払う費用。
・ 保険関連費用 : 火災保険や地震保険などの費用
・ 税金 : 売買契約書に掛かる「印紙税」、不動産を取得した時に掛かる「不動産取得税」など
● 諸経費
次に、マンション経営で発生する経費についてご説明します。
>> マンション経営で知っておくと得する10の経費
マンション経営の所得は「賃料収入-必要経費」ですので、経費計上額が大きいほど所得が減り、節税につながります。マンション経営のために必要な経費であれば、どんな小さな額でも領収証などを整理・保管しておきましょう。
・ ローンの利息 : ローンを組んで不動産を購入した場合の利息分
・ 減価償却費 : 経年劣化によって価値が下がった「劣化分」を金額で評価したもの
・ 保険料 : 火災保険や地震保険、住宅補償保険などの保険料が定期的な経費として発生
・ 交通費退去時の立会いなど、マンション経営に関わる交通費
・ 通信費 : 管理会社や入居者と連絡する電話代や郵便代などの経費
・ 宣伝広告費 : 入居者募集の広告などに必要な経費
・ 管理委託費 : マンションの管理業務(賃料徴収代行など)を管理会社に委託する場合の委託費用
・ 管理費、修繕積立費、修繕費 : 管理会社に支払う管理費や修繕積立費、原状復帰のための修繕費
・ 税金 : 固定資産税、物件取得時に掛かる登録免許税、不動産取得税、印紙税などの経費
・ その他 : 確定申告時の税理士への依頼費用、マンション経営に関わる接待交際費など
6章 マンション経営を失敗させないための税金の知識と節税対策
マンション経営のメリットで忘れてはならないのが節税効果です。
>> マンション経営で節税できるって本当?!
● マンション経営で知っておくべき税金
マンション経営で納税が必要になるのは次の4つのパターンです。節税効果を最大限に活用するためにも、不動産投資にかかる税金については正しい知識を身に付けておきましょう。
<物件取得時>
物件取得時には「不動産取得税」が課税されます。さらにマンション購入後、新たに購入した家具や賃貸人募集のための広告宣伝費などを運用コストとして確定申告で計上できます。物件取得時だけの経費もあるのできちんと整理しておきましょう。
<ローン返済中>
不動産経営で「収益」が得られれば「不動産所得」として、年1回、確定申告する必要があります。具体的には、賃貸収入から必要経費を差し引いた金額ですが、不動産所得以外の「給与所得」や「事業所得」がある人は、「不動産所得 + 給与所得 + 事業所得」を合算して「損益通算」することができます。そこから各種所得控除を差し引いた金額が課税所得になります。簡単な数式で表すと、次のようになります。
課税所得 = (「不動産収入 - 必要経費」 + 「給与所得」 + 「事業所得」) - 「各種所得控除」
>> マンション経営者なら知っておきたい確定申告の基礎知識
<マンション売却時>
マンションを売却する時には、譲渡価格から「取得費」や「譲渡費用」を差し引いた金額が「黒字」になれば、確定申告して「譲渡所得税」を納めなくてはなりません。
譲渡費用というのは、売却時に不動産会社に支払った仲介手数料や、売買契約書に貼る印紙代などのことです。取得費は、購入金額の他に不動産会社への仲介手数料、登記費用、不動産取得税、売買契約書の印紙税、リフォーム費用などがあります。
>> マンションを売却するときにかかる手数料と税金とは?
<相続時、贈与時>
保有するマンションを相続したり、贈与したりするときには節税効果を狙えます。2015年から相続税や贈与税の控除額が引き下げられて事実上の増税になりましたが、今後もこうした資産に対する課税基準は年々厳しくなる可能性があります。詳細は、税理士などに相談しましょう。
● 建物に適用される「減価償却」の凄い節税効果?
さらに、建物だけに適用される節税方法で、建物の取得費を毎年経費計上できるものに「減価償却費」があります。減価償却費は、建物の価値の減価分に合わせて税金の額を調整するものです。
たとえば、2000万円のマンションを一度に税処理してしまうと、その年だけで終わってしまいますが、建物には法律で定められた「法定耐用年数」があり、その年数に応じて建物の取得価格を分散して必要経費にできる仕組みです。たとえば耐用年数の残りがあと10年あったとすれば、「2000万円 ÷ 10年 = 200万円」になります。
つまり今後10年間、毎年200万円をマンション経営の経費として使うことができるということです。ちなみに、減価償却には一定金額を減価償却して行く「定額法」、そして一定の率で減価償却する「定率法」の2種類がありますが、現在、建物は定額法だけになります。
7章 マンション経営を失敗させないためのリスクへの知識と対応
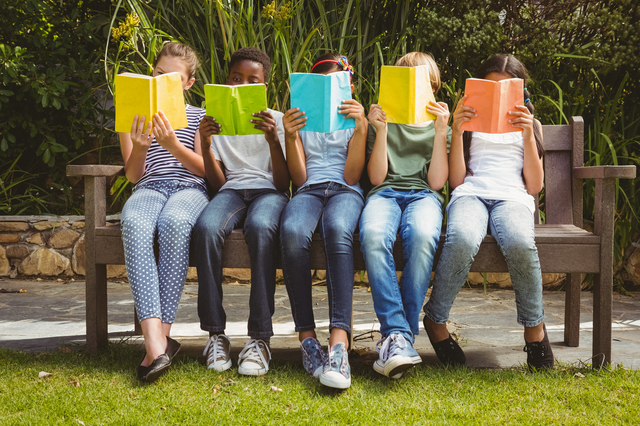 (写真=PIXTA)
(写真=PIXTA)
マンション経営にも、当然ながら様々な「リスク」があります。リスクをきちんと認識したうえで投資することで、初めて大きなリターンを得られるのがマンション経営の基本中の基本です。リスクを取らない投資にリターンはないのです。ではマンション経営には、どんなリスクがあるのでしょうか。
>> マンション経営 6 つのリスク
① 空室リスク
空室が発生すると、急激に資金繰り(キャッシュフロー)が悪化します。敷金、礼金なしの物件が増えたことで、ニーズに対応できなくなった物件はすぐに引っ越され、空室リスクは年々高まっています。
② 家賃滞納リスク
こうした事態を防ぐためには、入居審査を厳しくして保証人を付けたり、保証会社を活用するなど対策が必要ですが、あまり厳しくし過ぎると空室率が高まるなど弊害も出ます。
>> 不動産投資で破綻する原因は? 予防するために頭に入れておきたい最悪のケース
③ 家賃下落リスク
家賃は景気動向に左右され、下落するリスクもあります。ローンを組んでマンション経営をしていても家賃収入の下落で、ローン返済額の方が多くなれば、赤字経営になってしまいます。
④ 金利上昇リスク
マンション経営ではローンを組んでマンションの購入代金を工面します。それも、「固定金利型ローン」ではなく「変動金利型ローン」を組むのが一般的です。日銀によるマイナス金利の導入もあって超低金利時代ですが、今後マイナス金利が解除されて金利が上昇する可能性もあります。ローン金利が上昇すれば、ローンの返済金額も上昇することになります。
⑤ 低換金性リスク
マンションの売却に当たって低い価格でしか売れない「低換金性リスク」があります。中古の場合、新築と比較して低価格で査定されてしまうのが現実です。
⑥ その他のリスク
地震や火災、津波などの天災リスクがあります。建物には老朽化のリスクもあります。
>>地震リスクを考慮した、賢いマンションの選び方とは?
8章 マンション経営の利回りを理解して、収入を確保するための方法
マンション経営における収入の種類は2つあります。一つは毎月得られる賃料収入で「インカムゲイン」と呼ばれます。もう一つはマンションを売却した時に得られる売却益で、「キャピタルゲイン」と呼ばれます。
>> 本当はどうなの?マンション経営でどれくらい儲かっているのか?
また、マンションには次のような2つの「利回り」があります。この2つを把握しておきましょう。これもマンション経営の基本です。
表面利回り : 物件の購入価格に対する賃貸収入の比率
実質利回り : 表面利回りに対して、管理費などの諸経費を差し引いた、より正確に利回りを計算したもの
>>マンション経営で重要な2種類の利回りとは?
マンション経営の収益力を判断するときには「実質利回り」が重要になって来ます。そのためには、マンション経営で毎年かかる諸費用などをきちんと算出する必要があります。たとえば、マンションの経費には次のようなものがあります。
・ 管理費・修繕積立金
・ 火災保険料、地震保険料
・ ローン返済額
・ 固定資産税・都市計画税
・ 仲介手数料、広告宣伝費
マンションの立地やエリア、物件価格や物件の広さなど、そしてローン返済金額などによっても異なってきます。自分自身で不動産会社などにあらかじめ聞いて、年金コストを計算し「実質利回り」を算出しておくことが大切です。その上で、表面利回りとのバランスや近隣の似たような物件と比較して「収益力」の有無を判断するといいでしょう。
9章 マンション経営を失敗させないための資格や情報収集方法
マンション経営には不動産市場の動向や年間の収支、そして税金に至るまで様々な分野の専門的な知識が必要になります。マンション経営で成功するにはどのような資格が役に立つのか、どのように情報を集めたらいいのかを紹介します。
● マンション経営に役立つ資格
① 宅地建物取引士
不動産会社で不動産の売買や賃貸住宅の仲介をするのに不可欠な資格と言えば、国家資格の一つである「宅地建物取引士」です。不動産の売買や仲介は、すべて「宅地建物取引業法(宅建法)」に基づいて運用されており、この宅建法のスペシャリストが「宅地建物取引士」になります。
② マンション管理士
マンションの維持、管理、運営に必要な知識を豊富に持ち、マンションの所有者などから依頼されてコンサルタントを行うことができる資格です。さらに、修繕計画をどんなプロセスで建てればいいのか、修繕積立金の管理方法やその使い道についても、専門的な知識を持っています。
③ ファイナンシャルプランナー
マンション経営には、確定申告や収支計算の知識が不可欠です。とりわけ、税金の計算は毎年必ずやらなければならない作業になります。実際には、「決算書」「収支内訳書」「現金出納帳」といった確定申告に提出するための書類づくり、そしてこれらの資料を作成するための「各種領収書の整理」といった作業も必要になります。お金全般の幅広い知識を身に付けるためにファイナンシャルプランナーは理想的な資格と言えます。
● 資格取得の勉強は情報収集にも役立つ
マンション経営に役立つ資格を紹介しましたが、資格取得の勉強をすることで様々な情報を入手することも可能になります。たとえば、マンション市場の動向レポートなどに目を通すことになりますし、資格取得をサポートしてくれる業者であれば最新情報も入手できるはずです。資格取得とは別に、最新情報の収集もマンション経営で成功するプロセスの一つです。その他書籍やインターネット、不動産会社などから情報を得ることが重要です。
>> マンション経営で成功するための情報を収集する4つの方法
● サラリーマンがマンション経営で失敗しないために
サラリーマンは安定した収入を得られますので、ローン審査は比較的通りやすいといえます。サラリーマンをしながらのマンション経営は、入退室管理や賃料回収など様々な業務があるので、手間がかかると思われがちです。しかし、契約、家賃管理、入退室などの手続きは、一定の手数料を支払うことで管理会社に委託することが可能なため、サラリーマンをやりながら副業でマンション経営を行うことは十分に可能です。
>> サラリーマンは副業でマンション経営を実施できる?
● マンション経営の具体的な手順
マンション経営をするための具体的な手順について解説します。
>>実際にマンション経営をする際に必要な具体的手順とは
・物件のリサーチ
マンションを購入する前に、自分の希望条件を設定します。エリアについては、今後の人口流入や単身者の世帯の増加が見込める都心部がおすすめです。
・申込みと契約
希望条件と合致する物件があれば仮申込を行い、物件価格の10%ほどの手付金(金額は双方合意の元で決める)を支払い、契約をします。
・ローン審査、決済と登記
契約後にローンを組む場合は、ここで本申込をして引渡日当日に物件価格を支払います。その後、自分がその物件を所有していることを証明するための登記手続きをします。
・その後の実務
登記が完了したら入居者募集を行い、必要に応じて管理会社を選定し、家賃収入を得ます。マンションの清掃やメンテナンスのほか、賃借人の入退室時には修繕を行い、マンションの資産価値の維持に努めます。
10章 マンション経営の始め方
失敗しないマンション経営のための様々なノウハウを紹介してきましたが、マンションオーナーになるための心構えについてみてみましょう。
● マンション経営の注意点
マンションの経営者は、企業のオーナーと同じです。そのため、マンション経営を始めるにあたって、自分の属性を知ることや、適切なパートナー企業選びが重要になります。
>> マンションオーナーになるために知っておくべき4つのポイント
・ 自分の属性を理解する
マンション経営を始める時には、自分の属性(年齢や年収、勤務先など)を把握し、どうすれば金融機関からの信頼を勝ち取れるかを意識しましょう。もし今後マンション経営を拡大しようと考えるのならば、メインバンクからの信頼は非常に大事なポイントになります。
・ 節税とリスクについて理解する
マンション経営におけるリスクや節税についてしっかり把握しましょう。マンション経営の目的は「収益を生み出すこと」です。そのためには空室のリスクと賃料下落のリスクを極力下げるための「エリア選定」「物件選定」が大切になります。
>> マンション経営で知っておくべき5つのポイント
<東京エリアにおけるマンション経営の秘訣>
マンション経営の投資対象エリアとして、今後も高い賃貸ニーズが見込める東京都内のマンション経営の秘訣について解説します。
>> マンション経営の秘訣 東京編
・ 希少価値の高いエリアを選ぶ
希少価値の高いとは、例えば、港区の「三田」や「麻布十番」の付近のようなところで、このエリアはマンション用地が少ないため、賃貸でも空室リスクが少なく、売却する時にも高値で売りやすいところとなります。
・ 文京区エリア
住環境に優れ、「文教区」とも呼ばれている文京区のエリアも投資物件としては狙い目です。当区は「住みたい行政区」の4位で、様々な進学校が存在しています。大学校も多く、大学生の一人暮らしニーズも常に多いです。また、地下鉄、JR共に複数の路線が通っているので、交通利便性に優れているというメリットもあります。
・ 大崎
大崎駅はJR東日本の山手線、埼京線、湘南新宿ライン、さらに東京臨海高速鉄道のりんかい線が通っており、交通アクセスにとても優れています。オフィスビルが中心でしたが、その立地の良さからタワーマンションなど、居住用マンションに開発がシフトしていきました。居住者が増えたことで、目黒川沿いの遊歩道が整備され、駅の東西を結ぶ自由通路「夢さん橋」の開通など、居住者ための住環境はさらに向上しています。複数の大学のキャンパスもあり学生の住宅需要も旺盛なうえ、ファミリー向け、単身者向けなど、高い住宅需要が見込めるエリアです。
>>利便性の高さが好評の大崎 ―この30年で風景が一変した注目エリア
・日本橋浜町
古き良き日本の趣と現代的な景観が同居する、「日本橋浜町」もおすすめです。浜町は隅田川に面していることもあり、他の日本橋エリアに比べて緑が豊富です。特に中央区最大の区立公園である「浜町公園」は、ウォーキングコースや、野球・サッカーなどが行えるグラウンドも整備されていて、運動をするのにも適しています。東京駅から約2キロの徒歩圏内にあり、4つの地下鉄路線駅もあるうえに、高速道路の入口も近く、利便性に優れています。
<神奈川エリアにおけるマンション経営の秘訣>
神奈川エリアの魅力は何といっても「割安感」でしょう。渋谷や品川といった、サラリーマンにも学生にもニーズが高いエリアへのアクセスが良い割には、物件の価格が抑えられています。
>> マンション経営の秘訣 神奈川編
例えば川崎駅から品川駅へは約8分で行くことができますが、東京エリアで品川駅へ8分で行けるエリアを探すと、川崎エリアよりも物件の価格は上がります。品川駅を起点に考えている人にとって、川崎駅の価値は品川駅から同じ距離である都内のエリアと同じになる可能性が高いです。
そういったニーズを把握した上で、より価格の安い神奈川エリアを選べば、結果として利回りも高くなり、リスクを抑えたマンション経営が可能になります。都内でも、神奈川エリアでも、目安としては駅から10分以内の物件を選ぶことがポイントになります。
投資用マンション経営の失敗しない方法について紹介してきました。投資用マンションのオーナーになるんだという投資家マインド、経営者マインドを忘れずに、新たなチャレンジに投資してみてはいかがでしょうか。
最近のコラム
-
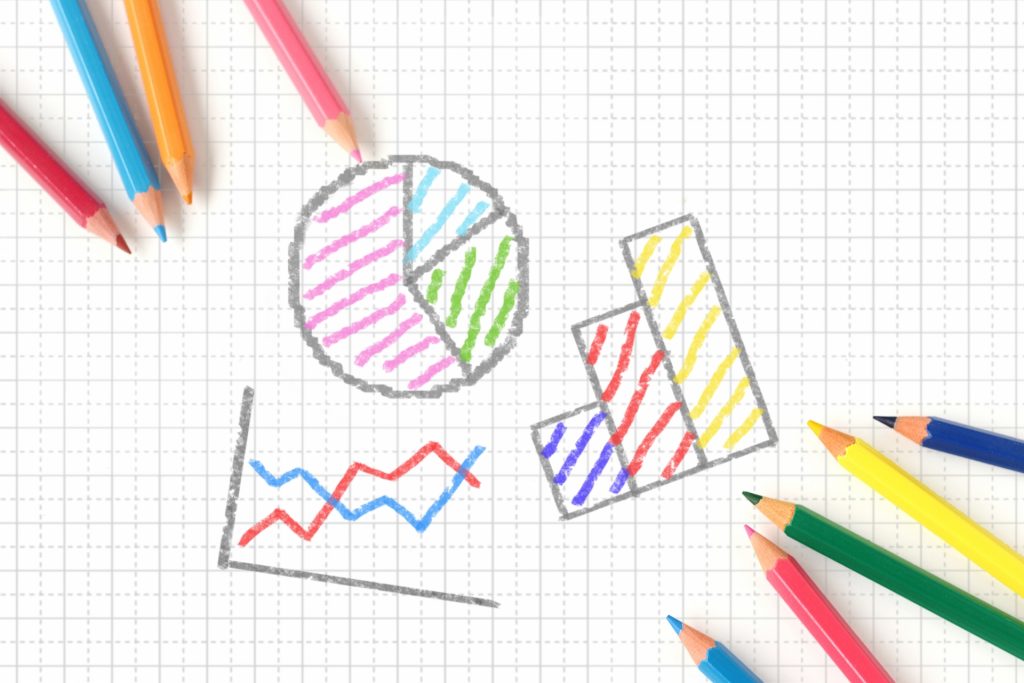
2019年上半期 マンション市場動向
-

始める前に知っておきたい。不動産投資における節税効果とは?
-

終活を意識し始めたら‥相続に備えて考えたい不動産投資という選択肢
-

不動産投資を始める前に要チェック!ハザードマップとは何か?
-

先進国で貯蓄率が増加傾向‥でも本当に貯金だけで大丈夫?
-

新型コロナより「家計・仕事」に不安を抱えるミレニアル・Z世代。不安の解決法は?
アーカイブ
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2011年10月
カテゴリー