マンション経営を、ゆっくり知って、じっくり考える。
将来の大切なことだから、あせらずじっくり考えて決めて欲しい。「マンション経営ラウンジ」は、マンション経営をゆっくり知って、じっくり考えていただけるお役立ち情報サイトです。


何に悩み、どんな行動をして、決断にいたったのか。ゼロからマンション経営を実現するサクセスストーリーで、一緒に楽しく学んでみましょう。

マンション経営をはじめる上で、知っておいて損はない基礎知識から市場、税制などの動向まで、アレもコレもまとめて情報収集しておこう。
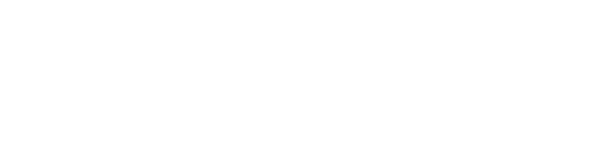
業界の第一線で活躍する専門家たちが今を語る。他と差をつける一歩先のマンション経営を実現するために、その道のプロ目線で見てみよう。


ヴェリタス・インベストメントがお贈りする⾃慢の物件を当社スタッフが住み⼿⽬線でこだわりポイントをレポートします。



不動産投資を検討する中で、「節税効果がある」という声を聞くことがあるでしょう。
今回は、不動産投資をすることで、具体的にどのような節税効果があるのか、税金の仕組みをわかりやすく解説します。また、注意すべき節税対策の落とし穴も紹介するので、不動産投資の節税効果に興味のある人はぜひ参考にしてみてください。
不動産投資は、リスクを抑えて安定的に資産形成ができる優れた投資方法です。そして、不動産投資を始めるメリットの1つに、節税効果があります。
不動産投資で節税できる税金は、所得税・住民税・相続税の3つです。それぞれの節税の仕組みを理解し、賢く不動産投資をしましょう。
所得税・住民税は、所得に一定の税率をかけて計算します。そのため、所得が小さくなるほど税金も少なくなることをまず理解しておきましょう。
所得には、給与所得、不動産所得などいくつかの種類があります。その中でも不動産所得と給与所得は、「損益通算」といい、相殺することが認められているのです。
不動産所得は、収入から経費を差し引いて計算します。そして、購入した建物の金額を、減価償却費として数十年に渡って経費化できます。建物の金額や構造、新築か中古かによって変わってきますが、初年度は多額の減価償却費を計上できることも少なくありません。すると、手元に資金が残っていても、不動産所得はマイナスになります。
このマイナスを、給与所得と相殺することで、給与に対して本来かかる所得税・住民税を節税できるのです。
相続税は、相続財産を評価したうえで、相続税率をかけて計算します。そのため、相続財産の評価額を抑えることが節税のポイントです。
財産の評価方法は、法律で定められており、それぞれに異なります。この財産ごとの評価方法の違いを活用すれば、不動産投資によって数百万円の節税効果を実現できる可能性もあるのです。
相続税において、現預金は金額をそのまま評価されます。しかし、現預金が土地建物になるだけで、評価額はぐっと下がります。さらにそれを賃貸すれば、40%以上の節税効果を狙うことも可能です。
節税効果は、不動産投資のメリットの1つです。しかし、節税だけを目的として不動産投資をすると、危険なケースもあります。
たとえば、「赤字にして所得税・住民税を節税できます!」といううたい文句には、注意が必要です。確かに初年度は、減価償却費や諸経費によって、帳簿上赤字になりやすい傾向があります。これに関しては、まったく問題ありません。
しかし、翌年も翌々年も赤字が続けば、結局手元の資金が底を尽きてしまいます。所得税・住民税の節税は期間限定のものと割り切り、その後は不動産をしっかり管理し、利益を出すことが大切です。
また、相続税に関しては、相続税がかかるかどうかをまずはシミュレーションしましょう。相続税には、「基礎控除」と呼ばれる税金がかからない範囲があります。基礎控除は、下記の計算式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
たとえば、妻1人子2人なら法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。相続財産が基礎控除の範囲内におさまる場合、そもそも相続税対策は必要ありません。
シミュレーションをする前から「相続税の節税」を強調する営業マンには、注意が必要です。
営業マンのうたい文句を信じて、節税だけを目的として不動産投資を始めるのは望ましくありません。節税の仕組みを理解し、自分の状況に当てはめたうえで、正しい投資判断をすることが大切です。
不動産投資を賢く活用すれば、節税効果はもちろんのこと、効率的な資産形成をはかれるでしょう。
]]>
終活や相続対策は、元気なうちにこそ取り組むべきです。最近では、50代60代のうちから終活や相続対策に取り組む人も増えてきました。今回は、不動産投資を活用した相続対策について、わかりやすく解説します。
これから終活や相続対策に取り組む人は、ぜひ参考にしてみてください。
8月の帰省シーズンに、実家と連絡を取り合った人も多いのではないでしょうか。2018年に相続法の改正が発表され、2020年7月までに順次施行された関係で、相続に関する関心度が高まっています。そのため、自然と相続の話題が出た家庭も少なくないでしょう。
楽天インサイトが実施した「終活に関する調査(2019年)」によると、終活をする理由は「家族に迷惑をかけたくないから」が75.9%と最多でした。続いて、「病気や怪我、介護生活で寝たきりになった場合に備えるため」46.4%、「自分の人生の終わり方は自分で決めたいから」38.2%といった回答が続きます。
一方で、終活への不安として、「何から手をつけたら良いかわからない」という回答が36.0%と最も多いという結果でした。
家族のために終活の必要性を感じ、財産整理をしたいと望みつつも、どのように手をつければいいか悩んでいる姿が調査結果から浮かび上がります。
今回は、財産整理の1つの方法として、不動産投資について紹介します。不動産投資が優れている点は、争族対策(親族間のトラブル対策)と相続税対策(節税対策)という2つの側面を兼ね備えていることです。
まず、争族対策についてみていきましょう。ワンルームマンションは1戸ごとに相続できるため、法定相続人の人数分のワンルームマンションに投資することで、親族間の争いを防ぐごとができます。共有名義になることもないため、それぞれが自由に物件を管理し、投資を継続できます。
複数の有価証券があり整理できていない場合や、有効活用できていない広大な土地がある場合、早めに現金化してワンルームマンション投資に回すことを視野に入れるとよいでしょう。
続いて、相続税対策についてです。
現預金は残高がそのまま相続税評価額になりますが、土地建物の場合、時価の6割から8割にまで評価額が減額されます。土地建物は、現預金と比べてすぐに現金化できず、流動性が低いからです。
また、土地建物を第三者に貸している場合、さらに評価額は減額されます。トータルでは、40%以上の評価減を狙うことも可能です。相続税は、相続税評価額に相続税率をかけて計算するため、評価額が下がれば節税になります。
親族間のトラブルを防ぎつつ、効果的に相続税を節税する――これが相続対策で不動産投資を活用する主なメリットです。
財産をスムーズに分割できないと親族間のトラブルになりますし、相続税評価額が高ければ、高額な相続税の支払いに苦しめられることになります。
そのため、終活や相続対策では、遺された家族の負担が軽くなるよう、財産整理をしておきましょう。まずは財産を洗い出して一覧にし、財産状況を把握するところから始めます。
そのうえで、分割しにくい資産は売却する等して、現金化します。同時に、相続税評価額を下げるため、ワンルームマンション投資を活用してみてください。
大切なのは、全体のバランスです。不動産が多く現預金が少なくなり過ぎても、相続税の支払いが難しくなってしまいます。相続税の納税資金を確保したうえで、効果的に不動産投資を活用しましょう。
]]>
災害大国の日本で不動産投資を始めるなら、災害リスクに気を配らなければなりません。今回は、ハザードマップを活用して、災害リスクを最小限に抑える方法を紹介します。災害に強い不動産を選んで投資することで、リスクを最小化し、利益を最大化しましょう。
2020年7月、熊本県を中心に広範囲にわたって大雨による水害が発生しました。日本は、地震や大雨、津波など自然災害の多い国です。不動産投資をするなら、災害リスクに細心の注意を払わなければなりません。
災害リスクへの対応策として積極的に活用したいのが、ハザードマップです。
ハザードマップとは、被災想定区域や避難場所、避難経路など防災に関する情報が記載された地図です。自然災害の被害を減らすことを目的として、国土交通省や地方自治体が公表しています。防災マップ、被害予測図、被害想定図といった名称で呼ばれることもあります。
ハザードマップは、火山、地震、津波、洪水などさまざまな自然災害に対応しています。
特に水害は、どんな地域でも起こる可能性があるため、しっかりチェックしましょう。浸水した際の水の深さまで確認し、購入予定の部屋が何階に位置するかを踏まえて判断するという考え方もあります。
地震については、新耐震基準の建物であれば、一定の安全性は担保されます。東日本大震災では、東北・関東のマンションの建物本体の被害について、「被害なし」が81.23%、「軽微」が16.13%という結果でした。築年数をチェックすることで、地震のリスクはある程度回避できると想定できそうです。
不動産投資を始めようと思った時、駅近の人気エリアなのに、割安な物件に出会うことがあります。そんな時は、念のためハザードマップを確認しましょう。過去に災害が起きたことで、買い手が見つからず、物件の評価額が下がっているという可能性があります。
万一そういった物件を購入してしまうと、災害リスク以外にも、売り手が見つかりにくいというリスクを抱えることになります。不動産を手放そうと思った時、売り手が見つからないと、そのままローンの返済を続けなければなりません。
売却のしやすさという観点からも、ハザードマップをしっかり確認することが大切です。
災害リスクに備える方法は、物件選びだけではありません。保険に加入することで、万一の事態になった時の金銭的な補償を確保しておくことも必要です。
加入するのは、主に火災保険と地震保険です。水害については、火災保険で補償を受けることができる場合も多いです。ただし、補償範囲はプランによって違うため、加入時には補償内容をしっかり確認しましょう。
地震は火災保険の補償対象外なので、別途加入する必要があります。火災保険に加入せず、地震保険にのみ加入することは認められていません。なお、噴火や津波、地震による火災などは、地震保険の補償対象です。
きちんと物件選びを行い、しかるべき保険に加入すれば、災害リスクを過度に恐れる必要はありません。
不動産投資を始めるなら、忘れずにハザードマップをチェックしましょう。自分だけで判断すると見落としが発生するケースもあるため、信頼できる不動産会社の担当者と一緒にチェックすると安心です。そのうえで、火災保険・地震保険に加入し、予期できない事態に備えましょう。
]]>
新型コロナウイルスの影響で世界中に不安が広がり、先進国を中心として貯蓄率が増加傾向にあります。貯蓄は大切ですが、本当に貯蓄だけでさまざまなリスクに備えられるのでしょうか?今回は、先進国の貯蓄率の上昇について考察し、正しいリスクヘッジの考え方を解説します。
恐ろしい事態を目の当たりにすると、自然と財布の紐は締まるもの。新型コロナウイルスの影響で、所得を貯蓄に回す割合が高まっています。
投資大国といわれるアメリカでも、2020年4月の貯蓄率は32.2%、5月の貯蓄率は23.2%でした。アメリカの貯蓄率は、2008年から現在まで、常に5~10%程度で推移してきました。そのため4月5月の貯蓄率は歴史的にみても異例な水準であり、人々の貯蓄への意識が急速に高まっていることがわかります。
ヨーロッパでも同様に、貯蓄率上昇の傾向がみられます。日本でも、2020年4~6月期には、約20年ぶりの高水準に達するという見通しがでています。
貯蓄をすれば、確かにその分だけ資産は増加するでしょう。しかし、貯蓄はそれ以上でもそれ以下でもありません。貯金をした分だけしか、資産は増えないのです。
超低金利の日本で、はたして貯蓄が正しい選択といえるでしょうか。効率的な資産形成を考えるなら、貯蓄以外の方法にも目を向ける必要があります。
たとえば、30年間毎月5万円を貯蓄した場合と、投資で運用した場合を比較してみましょう。
預金金利が0.001%とすると、30年後の資産は1,800万2,693円です。つまり、30年で2,693円しか資産が増えていないことがわかります。
一方、同じ金額を不動産投資に回し、利回り4%で運用したとしましょう。すると、30年後の資産は3,470万2,470円です。30年で1,670万2,470円も資産が増加したことになります。これが投資の効果です。
投資のメリットがわかっても、リスクが気になってなかなか始められないという人もいるでしょう。
リスクを抑えて堅実に投資をしたいと考えているなら、不動産投資が適しています。不動産投資の特徴は、ローリスク・ロングリターンです。つまり、リスクを抑えて、長期間に渡ってリターンを得られるということです。
不動産投資では、株式投資やFXのように、株価や為替レートを常にチェックする必要がありません。そのため、本業で忙しいサラリーマンや公務員でも、安定的に不労所得が得ることができます。
時代のニーズが移り変われば、企業の商品・サービスも移り変わり、場合によっては業績が傾いたり、倒産したりします。そうなれば、投資していた株式は無価値になってしまいます。
しかし、不動産は資産そのものに価値のある現物資産です。加えて、時代が変化したとしても、住まいの需要がなくなることはありません。特に東京都は、人口減少時代においても継続的に人口が増加し続けており、需要が安定しています。初めて不動産投資に取り組むなら、まずは東京都の物件を中心に取り扱っている不動産会社を選びましょう。
貯蓄は、一見するとリスクの低い資産形成の方法です。しかし、貯蓄だけで老後資金は足りるでしょうか。リストラや倒産といった万一の事態に、十分に備えられるでしょうか。こういった人生のリスクを総合的に加味すると、決して貯蓄の安全性が高いというわけではありません。
投資を過度に恐れるのではなく、リスクについて正しい認識を持ち、自分や家族を守るための選択をすることが大切なのではないでしょうか。
]]>
病気やボーナスカットより、長期的な家計に不安を覚える――。10代から30代の若者に実施したアンケート調査では、意外な結果が判明しました。今回は、アンケート結果をもとに10代から30代の若者が抱える悩みについて解説し、長期的な家計への不安に対して解決策を示します。
デロイト トーマツ グループは、ミレニアル世代・Z世代を対象とした「ミレニアル年次調査(2020年)」を公表しました。同調査は、第一次調査と追加調査の2回に渡って実施され、新型コロナウイルスによる社会的・経済的影響が調査されています。
最初にミレニアル世代とZ世代について簡単に説明します。ミレニアル世代とは、2020年現在26~37歳の世代、Z世代とは、2020年現在17~25歳の世代です。
ミレニアル世代は、インターネットが登場し始めた世代で、高いITリテラシーを持ちます。これに対して、Z世代はSNSが当たり前にある世の中を生きてきました。こういった時代背景の違いから、ミレニアル世代は理想を大切にし、Z世代は実用性に重きを置く傾向があるといった説もあります。
調査によると、新型コロナウイルスの感染拡大後、ストレスや不安を感じる頻度はミレニアル世代・Z世代ともに全体的には減少しています。しかしストレスの原因としてあげた理由を個別に確認すると、増加・減少の傾向がみられます。
ミレニアル世代で回答割合が増加したのは「長期的な家計」と「仕事とキャリアの展望」です。一方、Z世代では「長期的な家計」のみ回答割合が増加しています。ミレニアル世代が数年の勤務経験を持ち、働き盛りの世代であることも影響しているでしょう。
ミレニアル世代・Z世代ともに、短期的な視点より、長期的な視点で漠然と金銭的な不安を抱えていることがうかがえる結果となりました。
不安な気持ちを解消する最も効果的で前向きな方法は、不安に対処するための行動を起こすことです。長期的な家計に不安を抱えるなら、安定的に利益の見込める資産運用を始めましょう。
実際に行動を起こすことで、漠然とした不安は解消されます。あとはトライ&エラーを繰り返しながら、着実に利益を積み重ねていきましょう。
20代30代で長期的に利益をあげることを目指すなら、不動産投資が適しています。
不動産投資の魅力は、景気に左右されず、安定的に家賃収入が得られることです。コロナショックの影響で、株価は連日乱高下を繰り返しました。しかし、景気が悪化したからといって、家賃が株価のように変動するわけではありません。
衣食住の「住」を担う不動産投資は、不況に強い投資方法なのです。そのため、小まめに株価や景気をチェックして、一喜一憂する必要がありません。本業に注力しつつ、不労所得を得たい人には不動産投資が適しています。
20代30代のうちは、40代50代ほどまとまった資産は手元にないかもしれません。しかし、若いからこその大きなアドバンテージがあります。それは「時間」という目には見えない資産です。
毎月家賃収入を受け取る不動産投資では、資産運用の期間が生涯資産に大きな影響を与えます。毎年の利益が100万円とすると、資産運用を10年続けた場合の資産は1,000万円ですが、30年続けた場合の資産は3,000万円にものぼります。
不動産投資というと、ある程度まとまった資金を貯めてから取り組むものだというイメージを持つ人もいるでしょう。しかし、時間を味方につけられる20代30代こそ、不動産投資を始めるのに最適な年代といえます。
実際に不動産投資のメリットに気づき、20代のうちから物件を取得し、少しずつ買い増している人もいます。「時間」という資産は放置しているとあっという間に消費されていくものです。機会損失を生まないよう、早めに行動を起こすことが大切でしょう。
]]>
新型コロナウイルスの影響で一時期落ち込んでいた不動産投資市場が、早くも回復の兆しを見せ始めています。今回は、直近の不動産投資市場の状況を紹介し、不況に強い投資法である不動産投資の魅力を改めて解説します。不動産投資を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
JLLの調査によると、商業用不動産取引額は5月に落ち込んだものの、6月には急増しています。また、先行指標でもある鑑定の問い合わせ件数は、すでにコロナ前の水準に回復しました。5月に取引額が落ち込んだのも、対面手続きができないことによる取引の延期等が影響している側面もあります。
こういったデータをみる限り、コロナの影響で不動産投資が下火になることは考えづらいといえるでしょう。今後も、不動産投資は安定的な人気を誇り、取引数も堅調に推移していくと見込まれます。
そもそも不動産投資は、不況に強い投資法です。続いては、不動産投資が不況に強い理由を2つ紹介します。
金融市場に影響を与える大きな出来事が起きたり、天災が起きたりすると、株式市場は敏感に反応します。そもそも株式投資をしている人の大半は、余剰資金で投資をしています。そのため、不安になればすぐに株式を売却し、現金化してしまうのです。
一方、すぐに住居を手放す人はそれほど多くないでしょう。そのため、株式市場が落ち込むような局面でも、不動産投資においては安定的に家賃収入が得られる可能性が高いのです。住居は人間の生活にとって欠かせないものであることから、不動産投資は不況時にも安定収入を生み出してくれるのです。
不況になると、マイホームを購入するより賃貸で生活しようと考える人が増加します。そのため、必然的に投資用不動産のニーズが高まるのです。こういった理由で、不況は不動産投資においてはプラスに働く側面があります。
景気がいい時は、本業でも昇給が見込めますし、倒産リスクやリストラリスクも下がります。一方不況になれば、給与が減額されたり、リストラ・倒産といった事態になるリスクが高まります。そんな時こそ自分に適した投資法を選ぶことが重要といえます。
ひとくちに不動産投資といっても、さまざまな種類があります。投資初心者にも安心で、サラリーマンや公務員が本業に注力しつつ資産形成できるのは、ワンルームマンション投資です。
マンションを一棟丸ごと所有するとなれば、不動産投資ローンの金額は跳ね上がります。また、地震や津波といった天災によって物件が損傷を受けた時のリスクが高まります。
一方、ワンルームマンション投資なら、数十万円の元手で不動産投資を始めることができます。地震や津波といった災害リスクはあるものの、地域を分散してワンルームマンション投資をすれば、分散効果によってリスクは最小限に抑えられるでしょう。
ワンルームマンションはファミリータイプのマンションと比較しても需要が多く、リフォームやメンテナンスにかかる費用も少ないという特徴があります。収益をあげる仕組みもシンプルなので、1度成功すれば、その後は投資先を増やすだけでどんどん資産形成をしていくことができます。
コロナ禍の今こそ、人生のリスクヘッジとして、将来への備えとして、不動産投資を検討してみましょう。不況に強い不動産投資を始めておくことで、この先数十年の間に起こるであろう不況に備えることもできるのではないでしょうか。
]]>
コロナ禍の影響で、在宅勤務が増えたことなどにより、「東京の一極集中」のトレンドに変化があるのではないかという見方があります。一方で、実際に東京の人口を見てみると、依然として増加傾向が続いています。
今回は、不動産投資をしている方、不動産投資を検討中の方に向けて、コロナ禍の東京の人口への影響を解説します。
日本では、政治・経済・文化などすべての機能が東京に一極集中しています。都心部には数多くの企業があり、働き手の住まいも必要とされることから、必然的に不動産ニーズが高い状況が続いていました。
しかし、コロナ禍の影響で、「東京の一極集中」のトレンドが崩れるのではないかという意見があります。
政府はコロナの感染拡大を防ぐため、「密閉・密集・密接」の「3密」を避けるよう呼びかけています。しかし、人口が多く人の行き来が活発な東京では、なかなか「3密」を避けるのが難しいという現状があります。
コロナの感染者数をみても、国内では群を抜いて東京都が多い状況が続いています。また、観光産業を活性化するために実施されたGoToトラベルキャンペーンについても、東京は対象外とする方針が発表されました。
こういった状況を踏まえ、「東京の一極集中」のトレンドが崩れるという意見も散見されるようになりました。しかし、2020年5月1日時点で推計した東京都の人口は、初めて1,400万人を突破。コロナの感染拡大が続く中でも、依然として「東京の一極集中」が続いていることが裏付けられています。
日本全国でみると、人口減少に転じてしばらく経ちますが、東京都の人口は増加し続けています。出生率が4年連続で低下する中、東京都の人口が増加する理由は、社会増減(他県との移動増減)です。つまり、他県から東京都への流入によって、人口が増加しているのです。
東京都が発表した「人口の動き(2019年)」によると、東京都の人口は1997年より24年連続で増加しています。2019年の1年間では、9万4,193人増加しました。
2019年の変動要因をみると、自然増減(出生・死亡)がマイナスなのに対し、社会増減(他県との移動増減)はプラスとなっています。
そして2020年6月1日現在、人口総数は1,399万9,568人で、対前月比では3,405人減少していますが、対前年同月比では7万288人増加しています。
東京に進学・就職した学生や社会人が東京都以外に居住するなど、コロナの影響が多少は見られるものの、前年比では圧倒的に増加していることがわかります。こういった状況を踏まえれば、今後も「東京の一極集中」は続く可能性が高いといえるでしょう。
人口減少が続く中、地方物件に投資することは、リスクをともないます。不動産投資で一番恐ろしいパターンは、空室になり不動産を手放そうと思っても、買い手が見つからないことです。地方物件では、このパターンに陥るケースが多々発生しています。
しかし東京都の物件なら、心配いりません。安定的に需要があることから、空室リスクは最小限に抑えられます。また、万一不動産を手放したいと思った時は、売りに出せば買い手が見つかりやすいでしょう。こういった理由から、東京都の物件は不動産投資家にとって非常に人気があるのです。
コロナの影響が多少はみられたとしても、他県からの流入がある限り、東京都の人口は今後も増加していくでしょう。そうなれば、引き続き東京都の物件に人気が集中すると予想されます。
コロナの影響を過度に不安視して投資のタイミングを逃すと、かえって損をしてしまうかもしれません。人口動態を見たうえで、将来を予測し、正しい投資判断をすることが大切です。
]]>
新型コロナウイルスの影響で、生命保険に加入する人が増加しています。万一の事態に備える方法というと、保険をイメージする人が多いですが、実は選択肢は他にもあります。
今回は、人生のリスクヘッジと資産形成の2つを叶える方法として、不動産投資を紹介します。
株式会社エイチームフィナジーは、2020年1月から5月の間に生命保険に加入した20代から40代の男女を対象に、「新型コロナウイルス感染症の流行による生命保険加入への影響調査」を実施しました。
その中で、「新型コロナウイルスの流行は、生命保険加入及び検討することに影響を与えましたか」という質問に対し、「かなり影響を与えた」「やや影響を与えた」「影響を与えた」と回答した人の合計が72.8%となり、多くの人が何らかの影響を受けていることがわかりました。
また、「新型コロナウイルスの流行は、生命保険への加入、検討に対してどのように影響を与えましたか」と尋ねたところ、結果は下記のようになりました。
罹患時の収入減に備えること(53.0%)
罹患時の医療費(治療費・入院費)に備えること(52.7%)
万が一の際に遺された家族の生活費、教育費(46.3%)
※罹患(りかん) ‥病気にかかること
罹患した場合の収入源はもちろんですが、コロナ倒産が増えている中で、倒産リスクやリストラリスクについても考えなければなりません。
人生のリスクは実は身近なところにひそんでいますが、非常事態にならない限り、なかなか目が向かないのも事実です。コロナの影響によって気づくことができたことは、リスクに対して備えるチャンスといえるかもしれません。
リスクヘッジの方法というと、生命保険を思い浮かべがちです。しかし生命保険は、リスクが現実のものとならない限り、ほとんど意味をなさない場合もあります。高い保険料を支払っただけで、保険金を受け取る機会がなければ、トータルでみると損になってしまう可能性もあります。
それならば、最初から保険ではなく投資でリスクに備えるというのも1つの選択肢です。投資によって不労所得が得られれば、コロナ罹患時の収入減や医療費の心配も減少するでしょう。また、倒産やリストラといった事態にも冷静に対処できるでしょう。
投資の中でも、特に不動産投資は生命保険代わりになると言われています。それは、不動産投資ローンを組む時に団体信用生命保険(団信)に加入するからです。
団信に加入することで、返済者に万一のことがあった場合、保険金によってローンの残債が支払われます。そのため、家族はローン完済後の物件をそのまま手にすることができるのです。家賃収入が定期的に入ってくることで、生活費や教育費をまかなうこともできるでしょう。
2019年は老後2,000万円問題が話題になりました。不景気の影響で退職金は以前と比べて大幅に減少し、早期退職を募る企業も増加しています。今の時代、リスクに備えることはもちろん大事ですが、老後の生活費を貯めることも同じくらい重要になってきています。
生命保険でリスクに備えることはできても、高い保険料を支払い続けながら、同時並行で資産形成を実現するのは至難の業です。その点、不動産投資ならば、リスクヘッジと資産形成を同時に叶えることができます。
万一のことがあった場合は、団信でローン完済後の収益物件を家族に遺せる。何も起きなければ、退職時にはローン完済後の収益物件を手にし、不動産オーナーとして悠々自適の生活を送れる。2つの悩みを同時に解決できるのが、不動産投資の魅力です。
不動産投資で団信に加入することで、不要な保険を見直せば、かえって生活費が安くなる可能性もあるかもしれません。リスクヘッジや資産形成に関心があるなら、一度不動産投資を検討してみてはいかがでしょうか。
]]>
貯金目標を聞かれた際に、キリよく「1,000万円」と答える人もいるでしょう。では実際に1,000万円貯めるためには、何をすればいいのでしょうか?
今回は、社会人1・2年目を対象に実施されたお金に関する意識調査の結果を解説しつつ、貯金1,000万円を実現するための具体的なプランを紹介します。
ソニー生命は、社会人1年目・2年目の20歳から29歳の男女を対象に意識調査を行いました。初任給の使い道を尋ねたところ、社会人1年目では「貯蓄に回す」が58.2%と最も高いという結果でした。続いて、「生活費(食費など)に充てる」が40.6%、「親への贈り物を買う」が34.2%でした。
また、社会人2年目に、社会人1年目の貯蓄額を尋ねたところ、平均は45万円でした。内訳は下記の通りです。
10万円から20万円 25.0%
100万円以上 22.4%
50万円から100万円 16.8%
また、「0円」と回答した人も16.6%いるなど、貯金をする人・しない人が見事に分かれる結果となりました。一方、30歳時点での目標貯蓄額を尋ねたところ、平均は614万円で、内訳は下記の通りでした。
1,000万円から2,000万円 20.8%
500万円から600万円 18.6%
100万円から200万円 14.6%
社会人1年目は給与水準も低いことが多く、住んでいる場所によっては、生活費をまかなうだけでぎりぎりという場合もあるでしょう。しかし、年間平均貯蓄額の45万円では、30歳までに目標貯蓄額の平均値である614万円を貯めることはできません。
本気で貯金目標を実現したいと思うなら、早いうちから方法を検討し、計画的に資産形成をしていく必要があります。
貯金目標のボリュームゾーンが1,000万円から2,000万円だったように、とりあえず1,000万円を目標とする人はたくさんいます。では、具体的に1,000万円を貯めるために、どうすればいいのでしょうか。
30歳までに1,000万円貯めるには、22歳で就職したとすると、毎年125万円貯金しなければなりません。
「節約すれば何とかなる!」と考える人や、「昇給すれば一気に貯められるはず」と考える人もいるでしょう。しかし、給与が増えれば生活水準もあがり、結果として思うように貯金できないといったケースも少なくありません。
銀行口座に預金するだけで、貯金1,000万円を実現する人もいるでしょう。しかし、効率的なやり方かというと、そうではありません。投資を行うことで、貯蓄の効率を上げることができます。
投資にはさまざまな種類がありますが、20代で堅実に資産形成したいと考えるなら、不動産投資が適しています。今は定期預金に預けても、年間数千円しか利息は受け取れません。株式投資やFX投資は初心者にはハードルが高く、得をする可能性がある一方で、大きく損をしてしまうリスクもあります。
その点、不動産投資なら、継続的に家賃収入を得ることができます。不動産投資というと、大きなお金が動くイメージがありますが、不動産投資ローンがあるため、元手は数十万円ですみます。その後は、家賃収入からローンを返済しつつ、残金を貯金していくことができるでしょう。
もちろん、不動産投資ローンにも審査があり、誰もが必ず不動産投資を始められるというわけではありません。しかし、20代でも審査に合格するケースは多々あります。
もしローンがおりて不動産投資を始めることができれば、定期預金や株式投資と比べてはるかに効率的に、リスクを抑えて資産形成ができるでしょう。
30歳で貯金1,000万円を実現したい人は、預金での貯金や節約にばかりこだわりすぎず、視野を広げて不動産投資を検討してみてください。
]]>将来の見通しが立ちにくい今の時代、「マネ活」を始める人が世代を問わず増加しています。具体的な「マネ活」の方法を見てみると、定期預金が1位、株式投資が2位という結果でしたが、投資に苦戦している様子もうかがえました。
今回は、調査結果を分析するとともに、初心者が安定的に継続収入を得る方法として、不動産投資を紹介します。

アイネット証券は、20代から40代の女性を対象に「マネ活」に関する意識調査を実施。「具体的にどのような『マネ活』をしていますか?(複数回答可)」と質問したところ、下記のような結果が得られました。
円定期預金(31.2%)
株式投資(29.0%)
投資信託(22.1%)
NISA(つみたてNISAを含む)(21.3%)
外貨預金(12.6%)
iDeCo(10.3%)
FX(9.8%)
仮想通貨(9.5%)
ロボアドバイザー(4.5%)
不動産投資(2.8%)
1位に輝いたのは、元本割れのリスクが低い円定期預金。2位は真逆で、ハイリスク・ハイリターンの株式投資が続きました。
続いて、「『マネ活』をしていて難しいと感じることを教えてください(複数回答可)」と尋ねたところ、下記のような結果となりました。
専門知識の勉強(49.4%)
取引のタイミング(37.2%)
安定的・継続的運用(32.4%)
世界情勢などの情報収集(27.7%)
運用ノウハウの蓄積(24.9%)
リスクヘッジ(21.0%)
また、「政治関連の動きもチェックしないといけない」「コロナウィルスで株価が暴落し、見通しが立たない」「買ってすぐに価格が下がってしまった」といった意見もありました。マネ活を始めたものの、思うように資産形成ができず苦労している様子もうかがえます。
調査では最も取り組んでいる人が少なかった不動産投資ですが、実は投資初心者に向いている特徴がたくさんあります。不動産投資なら、初心者が直面しがちな「マネ活」の悩みを解消できる可能性もあるのです。具体的な不動産投資のメリットを2つ紹介します。
1つ目は、定期預金と比べて資金効率がいいことです。
定期預金の金利は、高金利なネット銀行でも0.2%程度です。これでは、100万円を運用しても年間2,000円程度のプラスにしかなりません。
一方不動産投資なら、元手の資金をほとんど使わず、毎年数万円の家賃収入を受け取ることもできます。もちろん、火災保険や固定資産税等の経費、ローンの返済もありますが、それを差し引いても、はるかに多くの金額を手元に残すことができる可能性もあるのです。
2つ目は、株式投資と比べて手間がかからないことです。
株式投資の場合、株価の変動を常にチェックしておかなければなりません。また、株価の変動要因ともなる、政治・経済に関するニュースを把握した上で、タイミングをみはからって売買する必要があります。会社員であれば、株価が気になるあまり、本業が手につかなくなってしまうケースも考えられます。
しかし不動産投資なら、最初の不動産会社選び・物件選びさえ慎重に行えば、その後はほとんど手間をかけずに家賃収入を受け取ることができます。不動産の管理は、不動産管理会社に委ねることがほとんどなので、時間をとられる心配もありません。そのため、本業に注力しながら資産形成をしたい人にとっても安心です。
女性が働きやすい環境が徐々に整えられてきたとはいえ、いまだに社会から受ける制約は数多くあります。「夫の転勤についていかなければ‥」「妊娠・出産を機に会社を辞めなければ‥」といった状況になることも考えられます。そんな時、不動産投資による継続収入があることは、大きな安心感になるでしょう。
会社で働くことだけがすべてではありません。不動産オーナーとして自分で道を切り開くという選択肢もあります。不動産投資は、将来の選択肢を広げてくれるでしょう。
不動産投資は、まだまだ注目度が高いとはいえません。だからこそ、優良物件に巡り会える可能性も高く、着実に資産形成したい人にとってはねらい目ともいえます。
「みんながしているから」という理由で定期預金や株式投資を選ぶより、メリット・デメリットをしっかり見極めたうえで、自分に合った「マネ活」として不動産投資を検討してみてはいかがでしょうか。
]]>2025年03月31日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第90回」公開しました。
2025年02月28日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第89回」公開しました。
2025年01月31日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第88回」公開しました。
2024年12月27日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第87回」公開しました。
2024年11月29日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第86回」公開しました。
2024年10月31日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第85回」公開しました。
2024年09月30日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第84回」公開しました。
2024年08月30日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第83回」公開しました。
2024年07月31日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第82回」公開しました。
2024年06月28日
不動産投資コラム「本当にあった不動産投資の失敗第81回」公開しました。
ヴェリタス・インベストメントは、投資⽤マンションの販売を軸に、不動産ディベロップメント事業を展開しています。
マンション⽤地の仕⼊れから、物件の開発、分譲販売、管理までを⼀貫体制でおこない、あらゆる⾯でハイクオリティなサービスのご提供を徹底しています。
また、オリジナルマンションブランドである「PREMIUM CUBE」シリーズは、東京都心部、横浜、川崎エリアの⼈気⽴地に限定したデザイナーズマンションで、業界に先駆けて著名なデザイナーやプロデューサー、ファッションブランドなどとコラボレーションした⾼付加価値なマンションの開発に取り組んでいます。
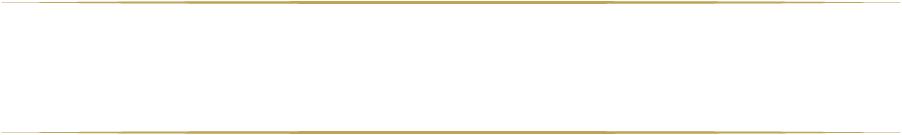
今なら資料請求いただいた方に、これからマンション経営をはじめる方にぴったりなツール3点をセットでプレゼントしています。お気軽にどうぞ。

川田社長が失敗しないマンション経営のやり方や不動産投資で最低知っておかなくてはならないベーシックな知識をわかりやすく解説。巻頭対談及び本文各項目のナビゲーターには、モデルとして活躍し、近年は作家・デザイナーとしての才能を発揮している押切もえさんを起用。不動産に関する知識ゼロの読者でも気軽に読むことができるマンション経営の入門書です。

マンション経営ってどういう仕組み? 何がメリットで、何がデメリットなの?サラリーマンやOL・公務員など、働きながら資産形成を考えたいという視点でわかりやすく解説。これからマンション経営をはじめようとしているビギナーの皆さまにぴったりのガイドブックです。

東京~横浜のブランドエリア、駅近立地のデザイナーズマンション、ヴェリタス・インベストメントのマンションブランド「PREMIUM CUBE」シリーズの最新物件パンフレット。ライフロケーションをはじめ、近隣の開発情報やデザインコンセプト、各種設備仕様まで、物件のすべてがわかるガイドブックです。