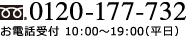マイナンバーでマンション経営はどう変わる? これだけは押さえておきたいマイナンバー対策!

マイナンバー制度の運用が2016年1月から開始しました。すでに、番号が記入された「通知カード」が送付されていますが、今後は徐々にこの個人番号(マイナンバー)が私たちの生活に関わってくることになります。では、マイナンバー制度によって私達の生活にどのような影響があるのでしょうか。
マイナンバーが使用される場面とは
マイナンバー制度の正式名称は、「社会保障・税番号制度」です。結婚や移転などで変わることがなく、生涯同一の番号によって識別されるため、国民総背番号制度とも言われます。
実際、すでに勤務先へマイナンバーを伝えている会社員も多くいるでしょうし、証券会社や銀行からもマイナンバー情報の提供を求められている人がいるのではないでしょうか。マンション経営などに関わっている人にとっては、2016年の確定申告から項目が新たに追加されマイナンバーを記入する必要が出てきました。さらにその際、配偶者控除や扶養控除を受ける場合にも、配偶者や親族のマイナンバーが必要になります。
では実際に、どんな場面でマイナンバーが使われるのでしょうか。
<社会保証関連>
・ 年金の資格取得や確認、給付
・ 雇用保険の資格取得や確認、給付
・ ハローワークの利用
・ 健康保険の利用
・ 生活保護など社会福祉の活用
<税金>
・ 確定申告や税に関する届け出など
<災害関係>
・ 災害者生活再建支援金の給付など
これらはすべて税務署や市町村など政府・自治体関係のものですが、これらに付随して今後は預金口座や証券口座の開設、維持、あるいは携帯電話の利用などにも、マイナンバーが必要になるといわれています。マイナンバー制度は、好むと好まざるとに関わらず国民の義務の一つになりつつあります。
マンション経営にはどんな影響が及ぶ?
さて、実際にマンション経営に携わる人にとって、マイナンバーとはどんな関わりが出てくるのでしょうか。確定申告書を書面で提出する場合は、納税者本人の個人番号通知カードの写しを添付することになります。確定申告にマイナンバーが明示されることで、税務当局にはこの納税者にどんな収入があって、どの程度の所得があるかが一目瞭然になります。
保有マンションを売却した場合、不動産の売却価格から「譲渡費用」などを差し引いて利益がある場合には、「譲渡所得」として確定申告をすることになります。その際、不動産を売却した相手が法人や不動産業者である個人の場合、売却金額が100万円を超したとします。すると、マンションを購入した側が「不動産支払い調書」を作成して税務署に提出するため、買った人=代金を支払った相手のマイナンバーが必要になります。逆に言うと、今後自分が投資用としてマンションなどを購入する場合には、売却した相手のマイナンバーが必要になることになります。
この他にも、マンション経営では家賃を支払った人からマイナンバーの提示を求められるケースがあります。たとえば、貸し出した相手が法人というケースは意外と多くあります。都心のワンルームマンションを事務所として営業をしているフリーランスなどが、法人を設立して営業しているといったケースも少なくありません。そうした法人から家賃など年間15万円を超える金額を受け取った場合には、その法人が「不動産支払い調書」を作成して税務署に届けることになります。支払い調書には「支払いを受ける者」として、不動産の所有者の住所、氏名、マイナンバーが記載されます。社宅として法人に貸している人などは、間違いなく支払い調書作成のためにマイナンバーの提示を求められるはずです。
不動産会社などに、あまり安易にマイナンバーは教えたくないと思うかもしれませんが、マンション経営では避けて通れないことと言えます。
罰則規定はないが、無視するより賢い活用法でチャンスを!
実際のところ、マイナンバーを確定申告書や支払い調書などに記載しなくても、罰則規定はありません。税務署などからは、マイナンバーの記載を求められるでしょうが、記載されていないからといって確定申告の受け取りを拒否されるなどということは、いまのところ考えにくいでしょう。
マイナンバー制度はこれまでの「年金番号」や「住民基本台帳カード」よりも、その規模や本気度という点で大きな違いがあります。これまでは政府に関わるサービスや事務手続きばかりがクローズアップされてきましたが、たとえば現在進められている「個人番号カード」は、運転免許書やパスポートなどの写真付き身分証明書を持たない人にとっては新しい「身分証」になります。
マンション経営に関わるものとしては「不動産登記」にもマイナンバーが必要になるというような案が出ています。この方法が採用されれば、登記の情報はすべて税務署の知るところとなり、相続や贈与の際には、より透明性が増すことが考えられます。そういう意味では、今後は海外口座に預けた預金なども含めて、きちんと税務署に申告して、着実に資産形成をしていく方法に限定されるようです。また、その方が変な節税法にとらわれるよりも効率的で、運用効果が高いのかもしれません。
マイナンバー制度はまだ始まったばかりです。不動産運用も含めて新しいビジネスの可能性があるかもしれません。マイナンバーに関する様々な情報にはアンテナを張りつつ、注意深く見守ることが大切と言えます。
(写真=PIXTA)
最近のコラム
-
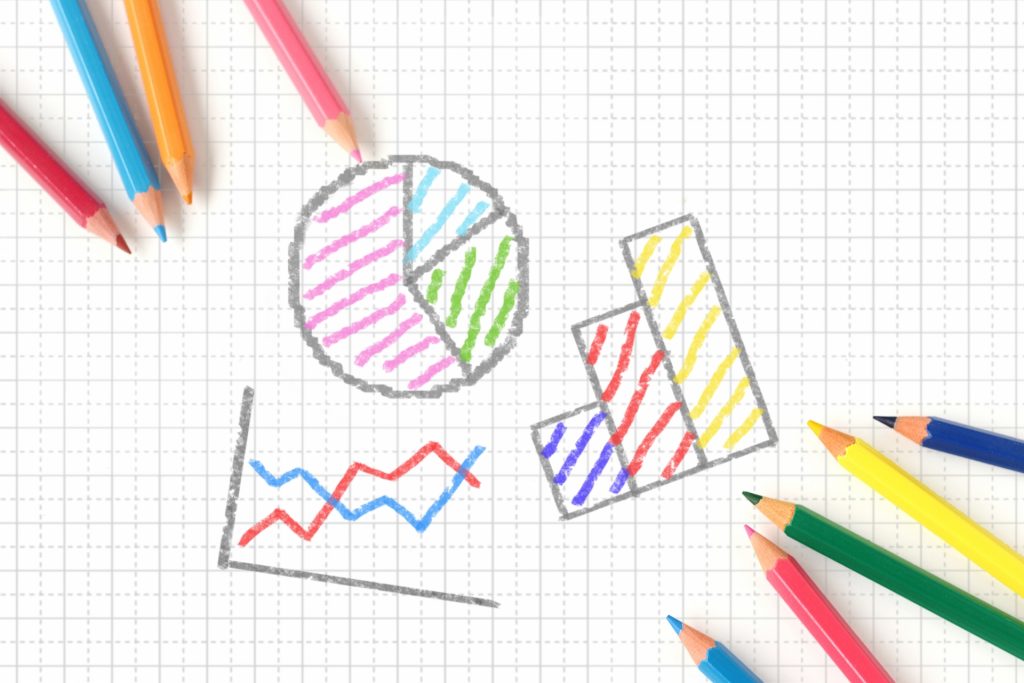
2019年上半期 マンション市場動向
-

始める前に知っておきたい。不動産投資における節税効果とは?
-

終活を意識し始めたら‥相続に備えて考えたい不動産投資という選択肢
-

不動産投資を始める前に要チェック!ハザードマップとは何か?
-

先進国で貯蓄率が増加傾向‥でも本当に貯金だけで大丈夫?
-

新型コロナより「家計・仕事」に不安を抱えるミレニアル・Z世代。不安の解決法は?
アーカイブ
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2011年10月
カテゴリー